DV被害の続きです。(前回はDV(デートDV)とは?をご紹介しました。)
DVは身体的な暴力だけでなく、精神的、経済的、性的等、あらゆる形の暴力の総称です。どんな形であっても、暴力は心とからだを傷つける重大な人権侵害になります。
最近は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」というものができましたが、犯罪の対象となるのは身体的な暴力のみであり、精神的な暴力に対しては対象外となっています。
だからといって、精神的な暴力が許されるわけがありません。
目次
以下、DVの種類です。
| ◆ 身体的暴力 | ◆ 精神的暴力 |
|
|
| ◆ 社会的隔離 | ◆ 経済的暴力 |
|
|
| ◆ 性的暴力 | ◆ 子どもを利用した暴力 |
|
|
あなたは相手がそのような行動に出るのは 「自分が悪いからだ」 と思い込んでいませんか?また、DVを”愛”だと勘違いしていませんか?
内閣府の男女共同参画局が平成24年4月に公表した「男女間における暴力に関する調査報告書(参考) *最下部に一覧抜粋」では、これまで結婚したことのある女性のうち、配偶者などから、「身体に対する暴行」や「精神的な嫌がらせ、恐怖を感じるような脅迫」「性的な行為の強要」といった暴力を受けたことが「何度もあった」人は10.6%という結果があり、およそ10人に1人がくり返し暴力を受けた経験があるというのです。
また、配偶者間における暴力の被害者の多くは、当然ながら女性であることが明らかになっています。
DVは遠い誰かの話ではなく、とても身近なことだということをわかってくださいね。実は姉妹や従姉妹や友だちが被害を受けていた・・・ということもあるかもしれません。
親しい人が交際相手との関係で困っているのではないかと感じたら、声をかけて話を聴いてみてください。
あなたのひとことで一歩踏み出す”気付く”ことに繋がるかもしれません。
また相談できる窓口があることもぜひ教えてあげてくださいね。
被害者に与える影響として、暴力による怪我にとどまらず、PTSD(post-traumatic stress disorder :外傷後ストレス障害) に陥るなど、精神的な影響を受けることもあります。
PTSDとは災害や犯罪等の後に生じる精神障害です。相手から繰り返される暴力に対して発症し、意図せずにつらい出来事が繰り返して思い出され、あらゆる物音や刺激に対して過敏に反応し、不眠やイライラが続いたりすることなどがあります。
(過去、私も夜道の電信柱の影に揺れていた黒いゴミ袋でさえ、自分を待ち伏せている相手ではないかとビクビクしたこともあり、何度も映像がフラッシュバックすることがありました。)
DVは暴力を受ける女性に影響を及ぼすだけでなく、傍で見ている子供たちにも深刻な影響を及ぼすことがあります。
直接子供に対して暴力を振るわなくても、母親への暴力が子供への暴力と同等の影響を及ぼすということを忘れてはいけません。 子供に心理的外傷を与える可能性があり、児童虐待のうち心理的虐待にあたるのですよ。
母親へのドメスティックバイオレンス(DV)に対して子供に現れた症状として、父親への憎悪・恐れや情緒不安定などがあげられます。
実際にそのような環境に育った方お二人に話を伺う機会があったのですが一人は「いつ親父を殺してやろうか。と毎日考えていた。」という衝撃的な言葉が印象的で、もう一人は父親との関係性が原因でうつ状態、パニック障害などの精神的な病気を(本人が)経験したことがあるということでした。
DVから女性を守るということは、子供たちを守るということでもあります。
| 【 子供に与える影響 】 |
|
このような現状からどうして逃げることができないのでしょうか。
それにもいくつか理由があります。
| ドメスティックバイオレンス(DV)から逃げない(逃げれない)理由 |
|
|
|
|
|
相手の愛情表現がこうだから仕方ない・・・、自分が悪い部分もあったかもしれないからと思い込んだり受け入れようとしたり、納得してはいけません。 暴力は犯罪です。
ドメスティック・バイオレンス(DV)
デートDV対処法
”暴力を振るわれる”事に対しては、あなたに原因はありません。
暴力を振るわない解決策があるのに、暴力を振るっている相手が悪いのです。
1番大事なことは、あなたが、自分が被害者であると気付くことです☆
そして、覚悟を決めて勇気を出して男性側(加害者)から離れる準備をして下さいね。 一人で悩まずに、誰かに必ず相談しましょう。
(男性側(加害者)に情報がバレないよう、友人知人親戚を含め慎重に相手を選んで)
①あなたと子どもの安全を最優先してください。
あなたと子供の安全が脅かされた場合は、110番通報をしてください。
暴力の証拠となるメモや写真や携帯の録音なども取っておいてください。
怪我をされられた場合は、病院に行き診断書をもらっていてくださいね。
②相談機関へ行きましょう!
◆ DV相談ナビ 0570-0-55210
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/
◆ 女性の人権ホットライン(参考)
「女性の人権ホットライン」は、配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。電話は、最寄りの法務局・地方法務局につながり、相談は、女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。
相談は無料、秘密は厳守されます。
女性の人権ホットライン 電話番号 0570-070-810 (全国共通)
◆配偶者暴力相談支援センター(参考)
「配偶者暴力相談支援センター」とは、配偶者からの暴力全般に関する相談窓口で、都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしています。また、市町村も自らが設置する適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすよう努めます。配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護、自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助、保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助などを行っています。ご利用は、都道府県によっては婦人相談所のほかに女性センター、福祉事務所などを配偶者暴力相談支援センターに指定しているところもあります。事前に電話で連絡した上で、相談等に行くことをお勧めします。
全国の配偶者暴力相談支援センター 一覧(参考)
http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/01.html
【支援センターの具体的な業務】
- 相談又は相談機関の紹介
- カウンセリング
- 被害者及び同伴者の一時保護(ただし、一時保護については、婦人相談所が自ら行うか、婦人相談所から、一定の基準を満たす者に委託して行うこととなっている。)
- 被害者の自立生活促進のための就業促進、住宅確保、援護等に関する制度の利用等についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助。
- 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡その他の援助。
- 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助 などです。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する支援内容
【加害者から逃れたい場合】
- 一時保護 / 自立支援
【加害者を被害者から引き離してほしい】
- 被害者への接近禁止命令(期間:6か月)
- 被害者の子または親族などへの接近禁止命令(期間:6か月)
- 電話等禁止命令(期間:6か月)
- 退去命令(期間:2か月)
- 詳しくは内閣府男女共同参画局 公式サイトをご覧ください
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html
◆NPO法人 全国女性シェルターネット 「女性のためのDV相談室」
夫や恋人からのDV(ドメスティック・バイオレンス)、デートDVなど、さまざまな暴力に悩む女性をサポートしてくれます。
http://nwsnet.or.jp/index.html
【その他 DV関連リンク一覧 】
| 相談内容 | 相談先 |
| 安全対策・緊急時の相談窓口 (暴力の被害など) |
全国被害者支援ネットワーク |
| 全都道府県警察または各警察署の相談窓口 | |
| 配偶者からの暴力全般に関する相談窓口 | 全国の配偶者暴力相談支援センター |
| 婦人相談所 | |
| つきまとい、ストーカー行為の被害についての相談 | 各都道府県の婦人相談所 |
| 離婚や借金・財産問題の相談 | 弁護士 (各弁護士事務所) |
| 就業支援の窓口 (生活の為のお金の確保) |
各社会福祉協議会 (生活福祉資金の貸付) |
| 各福祉事務所の生活保護係 (生活保護の申請) | |
| 各市区役所の母子担当窓口 (児童扶養手当・児童手当等の申請) | |
| ハローワーク (就職先の確保) | |
| 職場におけるセクシュアル・ハラスメントについての相談 | 全国の労働局雇用均等局 |
また、DVの被害者に相談された場合には、下記ご配慮ください。
- 相手の話をしっかりと受けとめてあげてください。
- 被害者の安全を確保してあげてください。
- あなたは悪くない! 自分を責めないで・・。と優しく伝えてあげてください。
- 病院・警察・相談員のところへなど、なるべく付き添ってあげてください。
- 指示・忠告・非難・批判をしないでください。(二次被害への拡大の可能性があります)(*彼女たちは本当に疲れています。怯え、猜疑心もあることでしょう。どうか心ある対応をお願いします。)
男女間における暴力に関する調査
平成26年度調査 概要版 一部抜粋(全文はこちら)
1 )配偶者からの被害経験
約5人に1人は配偶者から暴力を受けたことがある
2 )配偶者からの被害経験(男女別)
女性の約4人に1人は配偶者から被害を受けたことがあり、約 10 人に1人は何度も受けている
3 )配偶者からの被害の相談の有無
被害を受けた女性の約4割、男性の約8割はどこにも相談していない
4 )配偶者から被害を受けたときの行動
被害を受けた女性の約6割が「別れたい(別れよう)」と思っており、そのうち約1割は別れている
5 )子どもの被害経験
被害を受けたことがある家庭の約3割は子どもへの被害もみられる
6 )命の危険を感じた経験
被害を受けた女性の約9人に1人は命の危険を感じた経験がある
1 )交際相手からの被害経験
女性の約5人に1人は交際相手から被害を受けたことがある
2 )同居する交際相手からの被害経験の有無
交際相手と同居(同棲)経験がある女性の約3人に1人は被害を受けたことがある
3 )交際相手からの被害の相談の有無
被害を受けた女性の約4割はどこにも相談していない
4 )交際相手から被害を受けたときの行動
被害を受けた女性の約6割、男性の約4割が交際相手と別れている
5 )交際相手と別れなかった理由 (複数回答)
約半数が「相手が変わってくれるかもしれないと思ったから」
6 )命の危険を感じた経験
被害を受けた女性の約4人に1人は命の危険を感じた経験がある
1 )特定の異性からの執拗なつきまとい等の被害経験
女性の約 10 人に1人は特定の異性からのつきまとい等の被害を受けたことがある
2 )加害者との関係
交際相手・元交際相手が約4割、職場・アルバイトの関係者、友人・知人が約2割
3 )特定の異性からの執拗なつきまとい等の被害の相談経験の有無
女性の約8割は相談しているが、男性の約6割は誰にも相談していない
4 )命の危険を感じた経験
被害を受けた女性の約3割は命の危険を感じた経験がある
1 )異性から無理やりに性交された経験 -時系列比較-
女性の約 15 人に1人は異性から無理やりに性交された経験がある
2 )加害者との関係
交際相手・元交際相手が約3割、配偶者・元配偶者が約2割
3 )異性から無理やりに性交された被害の相談の有無 -時系列比較-
被害を受けた女性の約7割はどこにも相談していない
上記の結果をみていても、誰にも相談できずに一人で悩んでいる人が多いことが推察できます。決して自分を責めずに、まずは上記の関連相談場所や、DV相談ナビに電話をかけてみてください。 たった一度の人生ですから、自分を一番大切に慈しんで、愛してくださいね。誰もあなたのことを傷つけるなんて出来ないのですから。
DV関連書籍
◆DVの詳しい書籍・新刊などの一覧はコチラからチェックできます。

■毒になる親―一生苦しむ子供 (講談社プラスアルファ文庫)
スーザン フォワード (著), Susan Forward (原著), 玉置 悟 (翻訳)
子供が従わないと罰を与え続ける「神様」のような親
●「あなたのため」と言いながら子供を支配する親
●大人の役を子供に押しつける無責任な親
●脈絡のない怒りを爆発させるアル中の親
「毒になる親」に傷つけられた子供の心は、歳を重ねても癒されない。悩む数千人の人々を20年以上にわたってカウンセリングしてきた著者が、具体的な方法をアドバイスする“現実の希望”にみちた良い本です。

■傷ついたあなたへ―わたしがわたしを大切にするということ DVトラウマからの回復ワークブック (単行本)
レジリエンス (著)
自らもDV被害者である中島幸子氏が代表をしている、DV被害者のサポート団体、NPO法人レジリエンス。 この団体が作成した、DV被害者が自分自身でDVから脱出し、心の傷を癒し自分を回復していくためのセルフワークブック。全編、丁寧で優しさに満ちた素敵な本です。

■DVと虐待―「家族の暴力」に援助者ができること (単行本)
信田 さよ子 (著)
「家族の暴力」は援助者に向かって投げられた爆弾だ。DV・虐待の傍らには、いつも不気味な謎が蠢いている。 「当事者性の不在」という謎が…。
カウンセラーの著者が、さまざまな事例を挙げて解説する。
著者は、1995年12月に原宿カウンセリングセンターを開設、所長として現在にいたる。
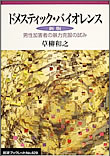
■ドメスティック・バイオレンス―男性加害者の暴力克服の試み (単行本)
草柳 和之 (著)
ドメスティック・バイオレンスの加害側への取り組みと、それによって派生する新たな見方を中心に書かれている。男性読者、例えば実際に暴力をふるっている人やその知人にとって、男性がパートナーにふるう暴力の問題をどう考え、その克服の道のりをどう歩むかについて、さまざまな示唆が得られるだろう。

■DVにさらされる子どもたち―加害者としての親が家族機能に及ぼす影響 (単行本)
ランディ バンクロフト (著)
これまで個別の問題として扱われてきたDVと児童虐待を包括的に捉え、DV加害者の親としての態度や行動に注目し、それがどのように子どもの日常生活を侵食し、家族機能全般にいかなる波紋を及ぼすかを浮き彫りにする。 DVや児童虐待に関わる相談機関のカウンセラーやソーシャルワーカーはもとより、児童福祉、司法や警察、医療機関の関係者などにとって、今後の支援の重要な方向性を指し示す一書。

■Q&A DVってなに?―この1冊でドメスティック・バイオレンスまるわかり (単行本)
番 敦子 (著)
この本はQ&A形式で構成されています。
掲載されている質問は、民間相談機関として、多くの相談者から尋ねられる質問の中からとりわけ必要性の高いもの、普遍性のあるものを選んで、取り上げました。また、自分が興味のある部分だけ、今困っている問題の部分だけ読んでも役に立つようになっています。

■DV被害者支援ハンドブック―サバイバーとともに (単行本)
尾崎 礼子 (著)
なぜ加害者は妻や恋人に暴力を振るうのか。アルコールのせい?怒りが抑えられないから?自分も子どもの頃に虐待されたから?など、一般に言われている原因は、ほとんどが加害者の言い訳として使われている。問題は加害者の価値観と態度に起因する。それを踏まえて、どのように被害者を支援していくべきか。アメリカでの実践に学ぶ、被害者の視点に立った支援のあり方。

■お父さん、怒鳴らないで―殴られるより苦しいよ! (単行本)
毎日新聞生活家庭部 (著)
ささいなことで大声を出し、家族を威圧するお父さん、「テメェー、バカヤロー」はやめてください。大切な家族を怒鳴りつけて、うれしいのですか?怒鳴る夫、怒鳴る父について寄せられた多くの投書は、言葉がいかに人の心を傷つけるかを物語っていた。
あなたの家族は泣いています。傷ついています。『毎日新聞』に寄せられた96人の投書をまとめる。
◆DVの詳しい書籍・新刊などの一覧はコチラからチェックできます。




